川原繁人
1980年生まれ。慶應義塾大学言語文化研究所教授。 カリフォルニア大学言語学科名誉卒業生。 2007年、マサチューセッツ大学にて博士号(言語学)を取得。 ジョージア大学助教授、ラトガース大学助教授を経て帰国。 専門は音声学・音韻論・一般言語学。 『フリースタイル言語学』(大和書房)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)等、著書多数。

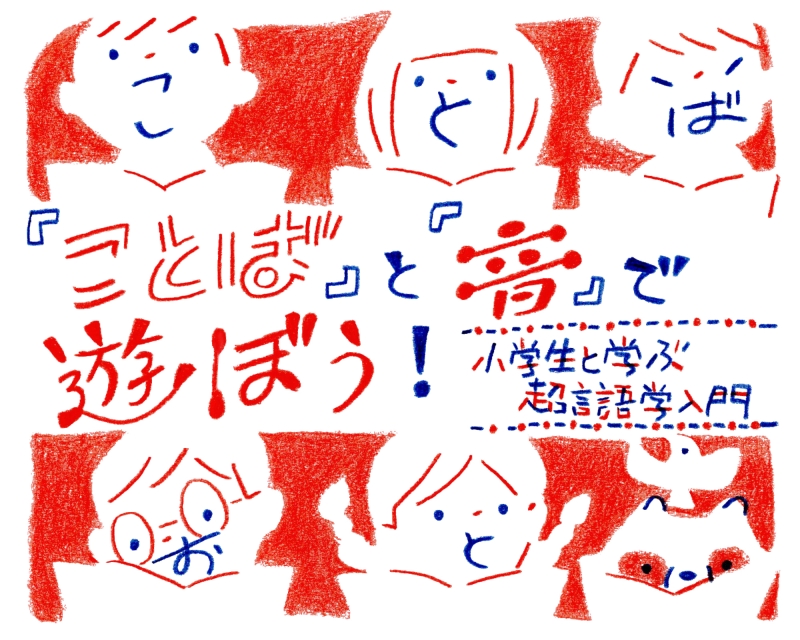 Illustration ryuku
Illustration ryuku
<今回の質問>
「なぜ世界のことばは共通して同じことばじゃないの?」 4年生・なぎ
「なぜ関西弁があるの?岩手のおじいちゃんもしゃべり方がちがう・・・なんで?」 4年生・さやは
川原 じゃあ、私なりに「何で言葉は違うんですか」っていう疑問に答えて、今日の講義を終わりにしようと思います。まず、言葉って変わるのよ。多分私がしゃべってる日本語とみんながしゃべってる日本語ってちょっと違うと思う。和光の中で流行ってる言葉とかない?
―― ない。
川原 そっか(笑) 和光の中にいたら和光だけで流行ってるかどうかわからないよね。例えば自分のこと「うち」って言う人、どれくらいいる?
―― 言ったりするわ。
川原 言ったりする? 私は言わないんだね。「うちは〜〜」って言うと、例えば川原家の話とか田中家の話に聞こえちゃうんだよ。だけど、みんな「私」っていう意味で「うち」って使うでしょう? そういうふうに言葉ってちょこちょこ変わっていくのよ。たぶん、みんなのおじいちゃん・おばあちゃんが話す日本語とみんなが話す日本語ってけっこう違うんじゃないかな。いつか機会があったら、注意深く聴いてみてごらん。あとは、日本語では、男の人と女の人でしゃべり方が違ったりするじゃない?
―― 「俺」とかって男の子のほうがよく使う。
川原 そう、良い例だね。だから、どうやって話すかっていうのは、自分がどういう人なのかを積極的にアピールする道具でもあるわけよ。服と一緒だ。自分の好きな服とかあるでしょう? どうやって話すかによって、自分がどういう人間であるかを表せるわけだ。話し方って自分を表現する道具のひとつなのね。ちょっと難しいことばでいえば、自分の「アイデンティティ」なのよ。
とにかく、ことばって常に変わっていくものです。すると、あるグループの人たちと別のグループの人たちで交流がなくなっていくと、それぞれのグループの言葉が別々に変化してっちゃうんだよね。そうやって時間が経っていくと、お互い通じないほど変わって、別の言葉になっちゃう。
こういうようなことばの変化を研究する学問があって、すごいことがわかってきました。今世界中のいろいろなところで話されている言語は、もともとひとつの言語だったってことがわかった。この図を見てみようか:

ヒンズー語やベンガル語は、今でいうインドのあたりで話されている言葉だね。英語、ギリシャ語、ドイツ語、フランス語なんかはヨーロッパの各地で話されている。この図に含まれているのはそれだけじゃなくて、東欧諸国で話されているポーランド語やさらに東で話されているロシア語。北の方にいけば、北欧のノルウェー語やスウェーデン語、それに、アフリカの大陸で話されている南アフリカ語まで入ってる。これらの言語って今は全然違う言葉で、お互いしゃべっても通じないんだけど、歴史をたどっていくと、もともとひとつの言葉だったことがわかってる。
これが、日本の内部でも同じことが起こっていることがわかっています。6年生は沖縄行ってきたでしょう? (注:和光小学校では、平和学習旅行として沖縄に行く)。これから行く人もいると思うから、沖縄の歴史や言葉も多分知っておくといいと思います。沖縄に行った6年生は、沖縄の言葉に触れてきた?
―― 触れてきた。
川原 どんなのがあった?
―― シーサー。
川原 そうだね、シーサーも確かに沖縄の言葉だ。シーサーは沖縄の置物だからね。他には?
―― ゆんたく。
川原 ゆうたくってどういう意味だった?
―― にぎやか。
―― おしゃべりだよ。
―― おしゃべりか。
川原 あとは?
―― めんそーれ。
川原 そうだね、「めんそーれ、沖縄」って、よく看板とかで見かけるよね。というふうに、沖縄には独特のことばがあります。でも、沖縄の中だけでも色々な言語があるんだよね。みんなが行く沖縄本島の言語もあるんだけど、例えば、宮古島っていうところに行くと、本島とは違う方言を話している。それに、奄美大島っていう、ちょっと鹿児島に近いほうに行くとまた別のことばがある(注:奄美は県としては鹿児島県に属するが、言語系統としては沖縄の各方言を含む琉球方言に含まれる)。奄美と沖縄の言葉って違うのよ。奄美の中でも北の地域と南の地域で言葉が違ってる。
ちょっとこの図を見てみようか。

川原 沖縄のことばだけじゃなくて、いわゆる日本語を考えても、九州だけでこれだけいっぱいあるのね。だから日本語の方言だけでもすごい種類があるんだよね。
川原 じゃあ、岩手の言葉とか関西弁とか、みんな、好き?
―― 好き。
―― 関西弁は好き。
川原 好き。何で好き?
―― なんかかわいい。
川原 かわいい。はい、みあ。
みあ 普段自分が言わない言葉だから。
川原 普段自分が言わない言葉だから好き。これ、素晴らしい考え方だと思います。はい、なつめ。
なつめ 自分たちが使ってる言葉に似てるんだけど、言葉がちょっと違ったりして面白い言葉とかになったりするから、すごい面白い。
川原 いいね。自分たちと違うから面白い。
―― みあとなつめにもちょっと似てるんだけど、自分の触れたことのない言葉を知れるというか、聞けることがいい。
川原 素晴らしいね。自分が知らない言葉だからいい。でもね、実は日本っていう国は、この素晴らしい方言たちをなくそうとしていた時期があるんですよ。江戸時代が終わって明治時代が始まりました。明治時代が始まったときに周りに強い国がいっぱいいました。アメリカがいた。イギリスがいた。オランダがいた。ロシアがいた。そんな国々に日本が一丸となって対抗するために強くなるぞっていう政策を取ったんだよね。その政策を「富国強兵」っていうんだけど。そのためには、さっきのバベルの塔の話みたいな話で、方言っていうのをやめてひとつの言葉をつくりましょうって言いだした。こうして、日本の政府は方言を禁止したんです。
どれだけ極端なことをしたかっていうと、例えば鹿児島なんかでは、方言札っていうのを使って、鹿児島弁を使ったら「私は方言を使いました」っていう札を掛けさせられて廊下に立たされていたらしい。私は、こういう方言の多様性を禁止するような政策は間違っていたんじゃないかと思っています。百歩譲って明治時代には日本っていう国を守るために必要だったのかもしれないけど、今でも方言を馬鹿にするような風潮って残ってるじゃない? 「なまっている」って言って、からかったり、馬鹿にしたりさ。でも、少なくとも現代では、こういう態度は時代遅れな考え方だと思います。
だから、みんなが「方言好き」って言ってくれたのがすごく嬉しかった。事前に質問を募集したときに「何で違うの?」って質問があったから、みんなの中に「違うと不便じゃない?」っていう気持ちがあるのかなと思ったけど、そうじゃなかったのかな。だったらいいなと思います。
「どんな言葉を話すか」っていうのは「自分がどんな人か」っていうことを表す方法のひとつだから、それがひとつになっちゃったらつまらないじゃない? 言語の多様性を大事する世の中になったらいいなっていうふうに私は思っています。
はるま あんなにいろんな方言があるのに僕が知ってるのは、ひとつの言葉だけ。それは明治時代に方言とかしゃべったらいけないと言ったのが影響してんのか。
川原 そうそう、そういうこと。明治政府が標準語っていうのをつくっちゃったんだよね。その影響で方言をしゃべる人が少なくなっちゃって。最近ではテレビとかメディアの影響もあって、ますます方言を話す人が少なくなっています。どこの地方で育っても、メディアで流れていることばが普通に聞ける時代になったからね。
でも、方言がどんどんなくなってしまうというのは、すごく残念な話ですよねっていうのが今日伝えたかった最後のメッセージかなと思います。もし「自分がなまっている」って悩んでいる人がこの中にいたら、そんな悩みは間違っているって知って欲しいし、もちろん、方言をからかうなんていうのはもってのほか。それから、これから生きていく上で、自分の方言に悩んでいる人に出会ったらちゃんと励ましてほしいと思います。
これが私からの最後のメッセージ。今日はありがとう!楽しかったよ。ぜひ、感想を聞かせてね。
(了)
2022年12月14日 学校法人和光学園 和光小学校の教室にて
1980年生まれ。慶應義塾大学言語文化研究所教授。 カリフォルニア大学言語学科名誉卒業生。 2007年、マサチューセッツ大学にて博士号(言語学)を取得。 ジョージア大学助教授、ラトガース大学助教授を経て帰国。 専門は音声学・音韻論・一般言語学。 『フリースタイル言語学』(大和書房)、『音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む』(朝日出版社)等、著書多数。